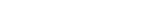現在でこそ都市部をはじめ電気水道の供給はあたりまえのように感じられますが、端島ではこれらライフラインの確保にも多大な苦労が
伴いました。電力の供給は炭鉱という島の特性から、かなり古くから発電所により供給されていましたが、反面湧水が一切ないこの島では、
水の確保がその歴史を通して常に重要な課題で、文化7年(1810)の露出炭発見から明治23年(1890) の三菱社の管理下にな
る迄の間のしばしばの休坑も、水の確保の困難さに大きく関わっていました。
端島の水の確保は大きく3つの時代に区分できます。蒸留水の時代、給水船の時代、そして海底水道の時代です。三菱社の管理下になっ
てとりあえず水の確保は安定しますが、それでも蒸留水および給水船の時代には、水券の発行による配給制度の導入や、生活用水の海水利
用、浴場や洗濯場などの大量水消費場所の共同化による節水を実施することで水の確保をしてきました。昭和32年(1957)、日本初
の海底水道が敷設されて水確保の心配はなくなりますが、しかし水の配給によってはぐくまれた共同体意識や、共同炊事場・洗濯場などの
コミュニケーションの場で培った連帯意識はその後も失う事なくこの島の住民に存続しました。画像は堤防南部に残る海底水道の取込口。