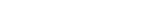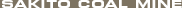
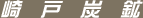
長崎県の北寄り、佐世保から高速艇で
約1時間の洋上に浮かぶ蛎浦島に発展し
た崎戸炭鉱は、明治40年(1907)
から九州炭鉱汽船によって開発が進めら
れましたが、昭和15年(1940)に
端島と同じ三菱の経営下になり、昭和4
3年(1968)閉山した、三菱にとっ
ては九州で最大規模の炭鉱でした。
かつてはその過酷な労働条件から「一
に高島、二に崎戸、三に端島の鬼ヶ島」
とまで言われた時もあります。
現在では鉄骨による施設こそないもの
の、前出の福浦坑の捲座(<捲座>参照
特に発電所煙突や選炭施設(右)などの
鉱業所関連施設が多く残存しているのが
印象的です。
また崎戸町歴史民族資料館の一部で炭
鉱時代のことを紹介しています。

コンクリート部分のみ残る巨大な選炭施設跡


頂上に植物を生やしながら残存する福浦発電所煙突跡

資料館入口の横に残る油倉庫跡


独身炭鉱夫の寮<平和寮>2階の室内

独身炭鉱夫の寮<平和寮>内の共同浴場跡


美崎(左4棟)と菅峰(右奥2棟)の妻帯者鉱員住宅棟跡

唯一鉄筋造だったため残っている昭和小学校跡


福浦会館(または崎戸劇場)といわれた映画館の映写室跡

外階段の基部のみが残る福利厚生施設<共楽館>跡


遊戯具が草むらの中に残る東峰遊園地跡

端島と同じ海水だった崎戸塩水プール跡